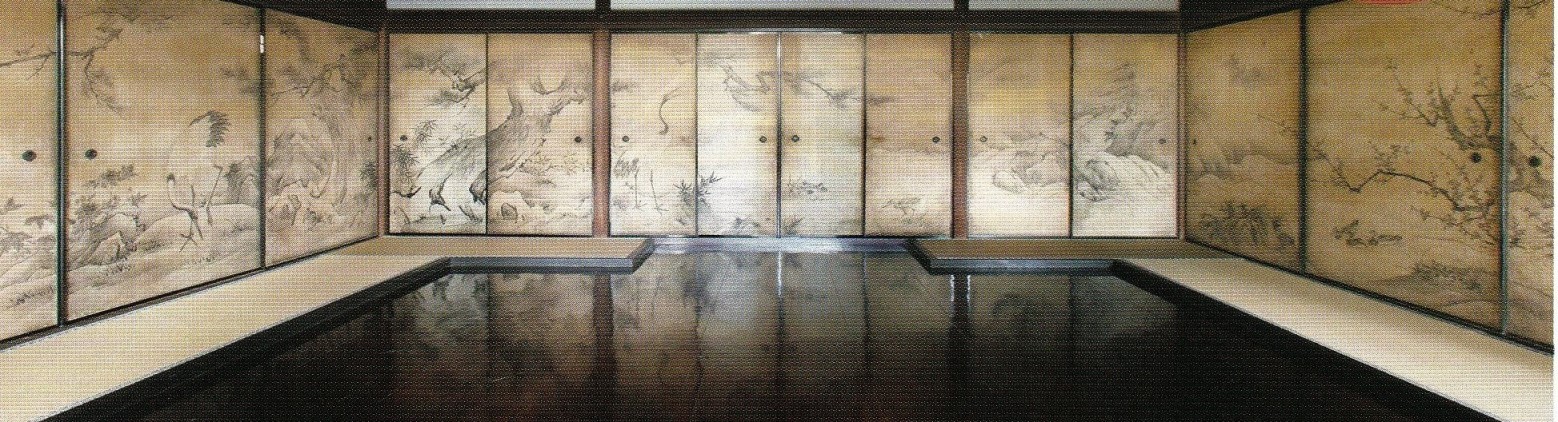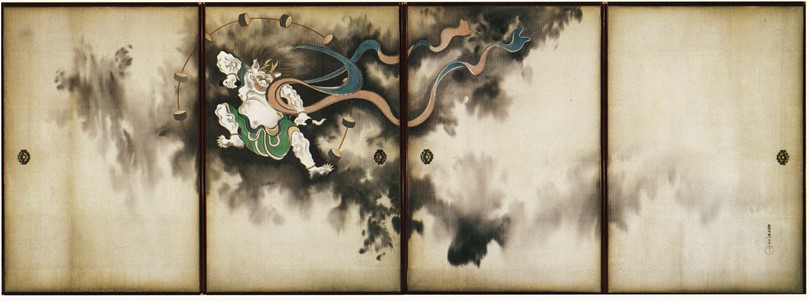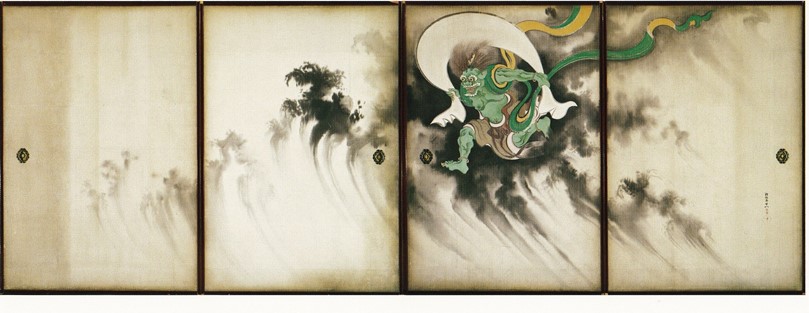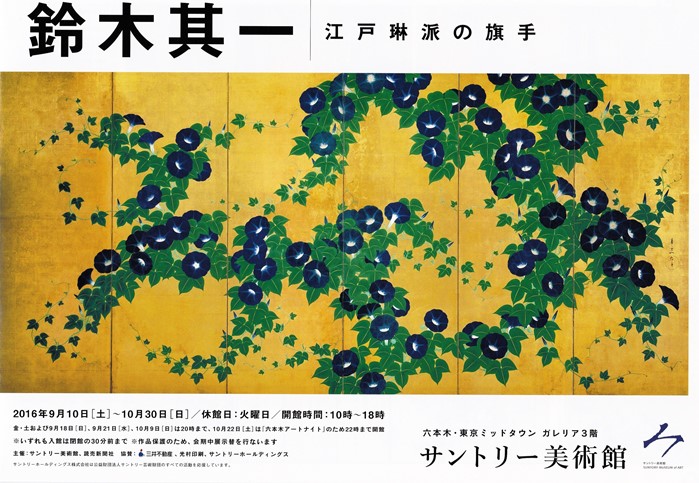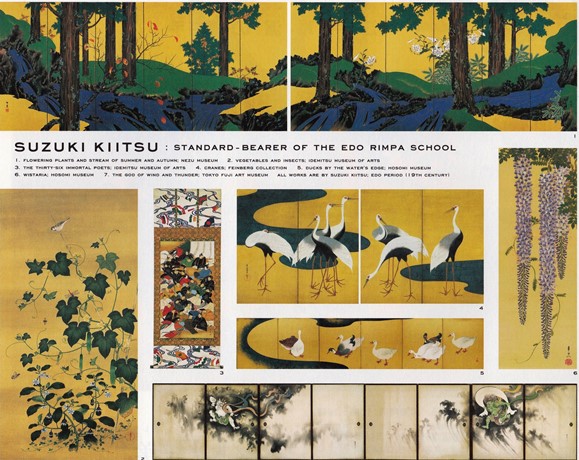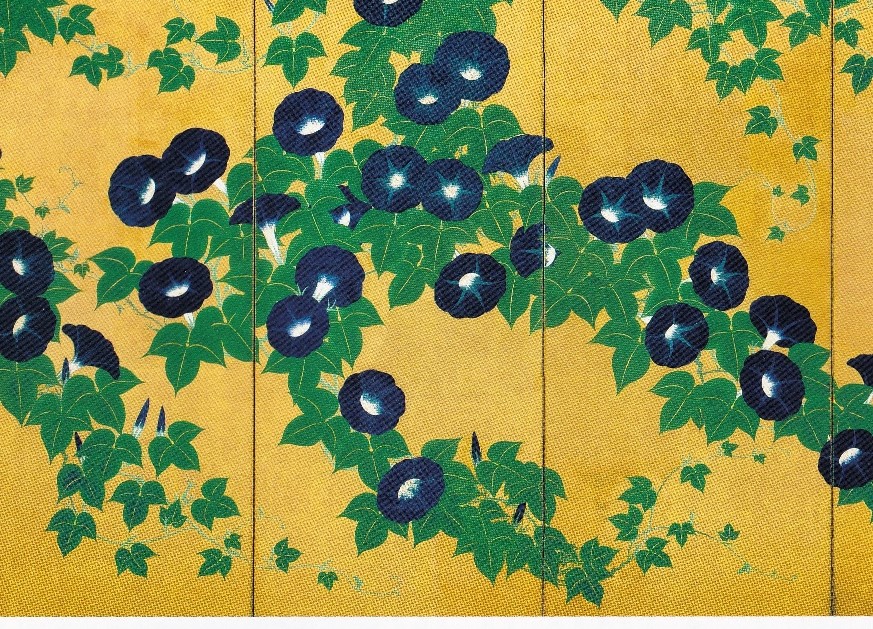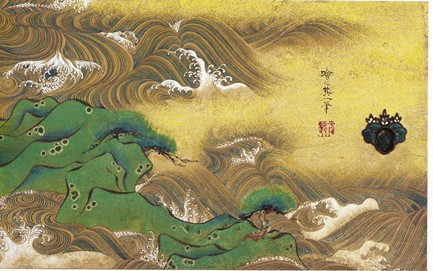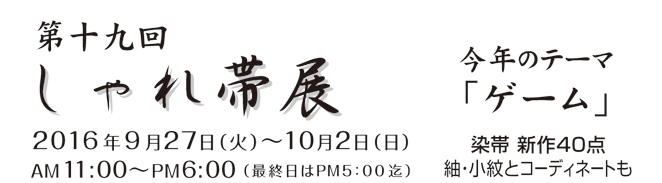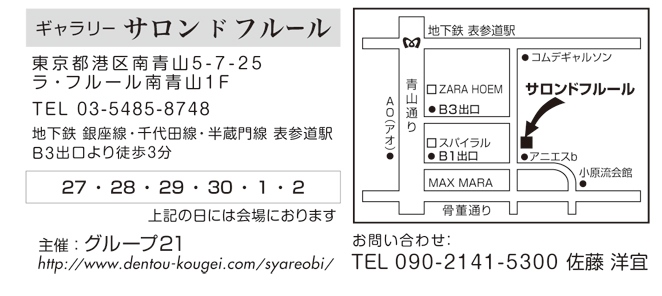2017,01,04, Wednesday
謹賀新年昨年中は皆様に大変お世話になりました。
今年もどうぞよろしくお願いいたします。
このHP、ブログにはぼかし屋友禅あてのメール連絡票
「お問い合わせ票」が付いております。
ぜひお読みいただいての感想、ご質問、各種ご指摘など、
お気軽な送信をお待ちいたします。
この年明けは色差し作業をしながらラジオで除夜の鐘を聞きました。
それでも毎年恒例、ウィーンフィル、ニューイヤーコンサートをテレビで楽しみました。
パイナップル↑
毎年注目のお花の飾り付け。今年は、色調としてはシック。
実はかなり面白い取り合わせでした。
指揮者のグスターボ・デゥダメル氏がベネズエラの出身だからか、
中南米原産の蘭とアマリリスが多用されていて、おまけに、
パイナップル↑
パイナップルが飾られています(^^)/
よく見るとかなり多く使われていて、
パイナップル↑
ほら、コンサートマスターの足元にもパイナップルが!!楽しいですね。
パイナップルと花々がよく溶け合っていて素敵です。
毎年このコンサートの花の飾り付けは友禅屋さんにとって参考になります。
解説によれば、指揮のグスターボ・デゥダメル氏は35歳。ニューイヤーコンサート史上最年少。若々しい新しい試みのある選曲をしているそうです。
初選曲の中に懐かしい曲がありました。
フランスの作曲家、ワルトトイフェルのワルツ「スケートをする人々」です。
私を含め一定以上の年齢層では知名度が高く、曲もよく知られているはず。
小学校の音楽の教科書に、木琴などを使った合奏曲として載っていましたから。
小学生向けに短くやさしく編曲されていて、かなり長期にわたって教科書に載っていたようです。
題名は「スケーターズワルツ」だったと記憶しています。
この演奏で打楽器奏者が変わった鈴を鳴らしているのが写りました。
算盤のコマが鈴になっているような楽器。
枠を叩いて微妙な鈴の音を響かせていました。
懐かしい、小学校、と言えば、
昨年はなんと母校の東京都、東久留米市立第六小学校で、4年生たちの伝統工芸体験教室に講師として参加する機会がありました。
懐かしい校舎の中を、実にン十年ぶりに歩きました。
残念ながら写真は校舎だけ。
個人情報保護の観点から、講師として生徒さんと一緒の写真は撮影が許されませんでしたが、伸子針で怪我をしないかハラハラしつつも、楽しく生徒さんと過ごしました。
今年もいくつか体験教室のお役が回ってきそうです。
制作だけでなく、こちらも頑張ります。
お知らせ | 01:08 PM | comments (x) | trackback (x)